御樋代(みひしろ)
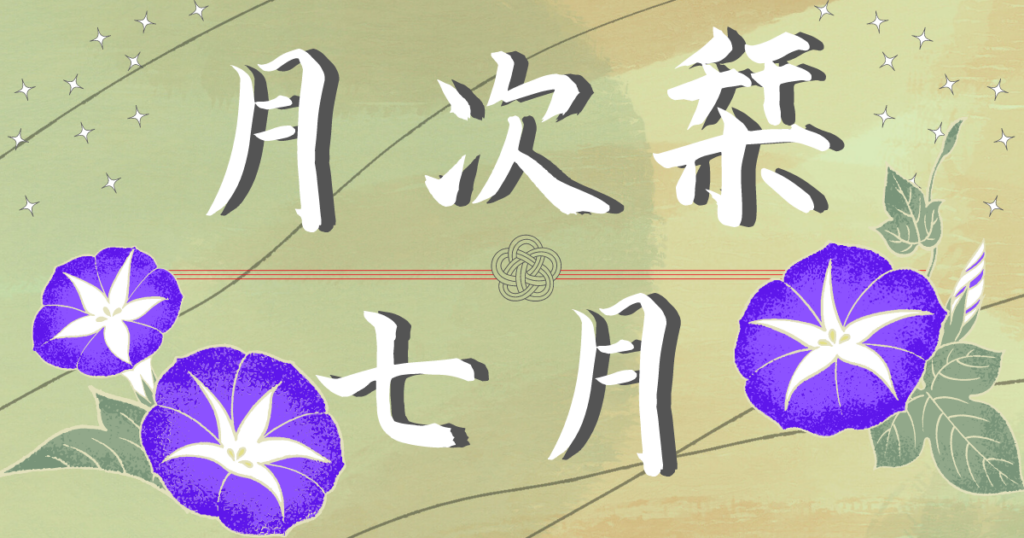
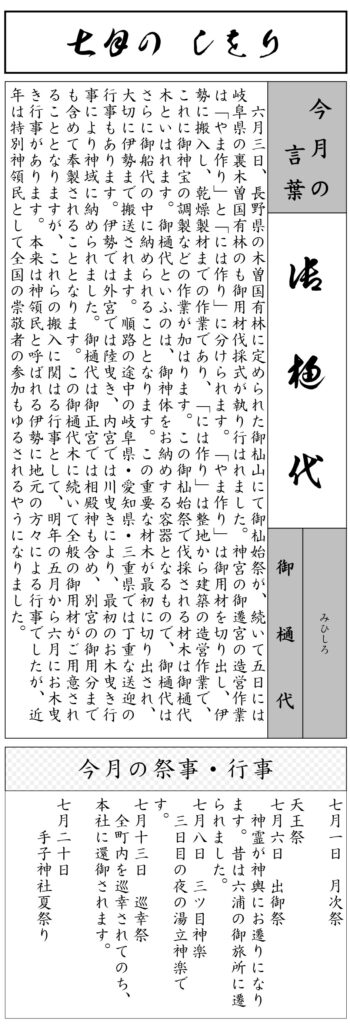
六月三日、長野県の木曽国有林に定められた御杣山にて御杣始祭が、続いて五日には岐阜県の裏木曽国有林のも御用材伐採式が執り行はれました。
神宮の御遷宮の造営作業は「やま作り」と「には作り」に分けられます。
「やま作り」は御用材を切り出し、伊勢に搬入し、乾燥製材までの作業であり、「には作り」は整地から建築の造営作業で、これに御神宝の調製などの作業が加はります。
この御杣始祭で伐採される材木は御樋代木といはれます。
御樋代といふのは、御神体をお納めする容器となるもので、御樋代はさらに御船代の中に納められることとなります。
この重要な材木が最初に切り出され、大切に伊勢まで搬送されます。
順路の途中の岐阜県・愛知県・三重県では丁重な送迎の行事もあります。
伊勢では外宮では陸曳き、内宮では川曳きにより、最初のお木曳き行事により神域に納められました。
御樋代は御正宮では相殿神も含め、別宮の御用分までも含めて奉製されることとなります。
この御樋代木に続いて全般の御用材がご用意されることとなりますが、これらの搬入に関はる行事として、明年の五月から六月にお木曳き行事があります。
本来は神領民と呼ばれる伊勢に地元の方々による行事でしたが、近年は特別神領民として全国の崇敬者の参加もゆるされるやうになりました。
